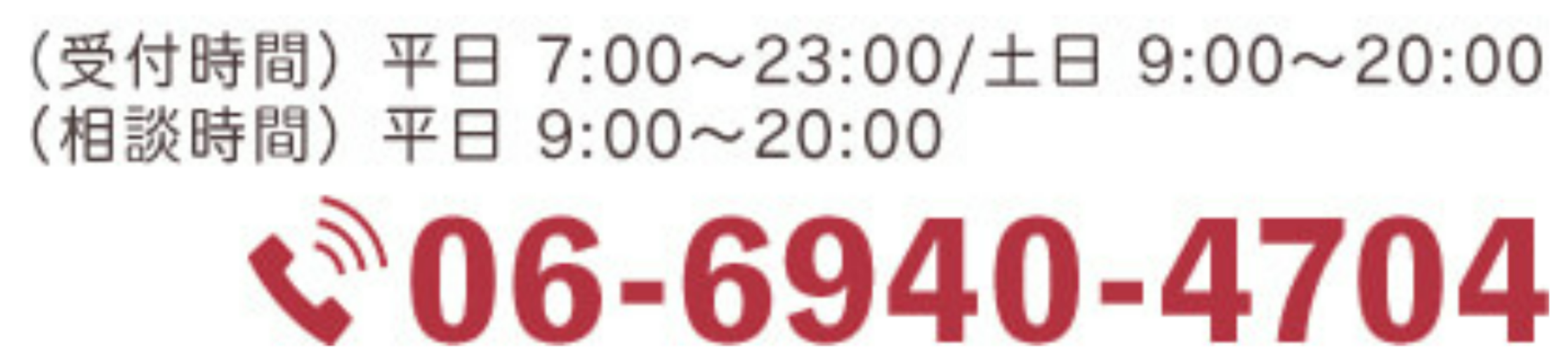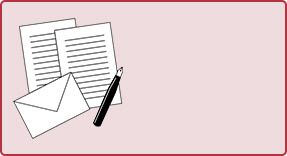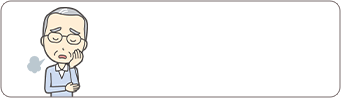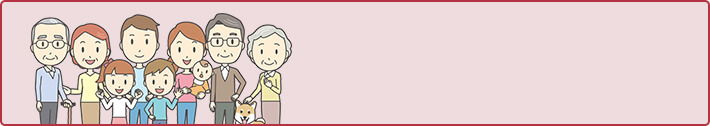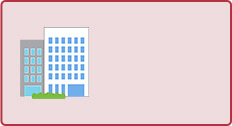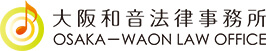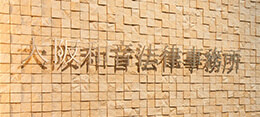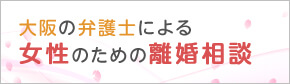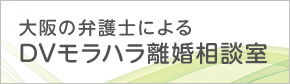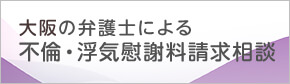相手方の弁護士から通知書が届いた
紛争の相手方から、弁護士名で「今後の連絡は全て弁護士宛にしてほしい」、「期限までに○○について回答してほしい」、「期限までに○○円を支払ってほしい」といった内容の通知書が届くことがあります。
突然このような通知書が届いた場合、どう対応すべきかお悩みになる方もいらっしゃると思います。
今回は、相手方の弁護士からこのような通知書が送られてきた場合にどう対処すべきかについてご紹介いたします。
「受任通知」の送付
弁護士が依頼者からの委任を受けて代理人として活動していくことになると、多くの場合「受任通知」と呼ばれる通知書を紛争の相手方に送付します。
受任通知に記載される内容は様々ですが、少なくとも弁護士が依頼を受け代理人となったことや今後の連絡に関しては全て本人ではなく弁護士宛にしてほしいことが記載さ れていることが通常です。
「今後の連絡は全て弁護士宛にしてほしい」と書かれていると、相手に伝えたいことがあっても全て弁護士を通さなければならないのかと疑問に感じる方もおられると思います。
このような連絡先の制限により相手方への連絡が法律上一切許されなくなるというわけではありませんが、弁護士は連絡や交渉の窓口を一本化するという目的で受任通知に「今後の連絡先を弁護士にしてほしい」ということを記載しています。
そのため、仮に相手方本人と直接連絡を取って、相手方本人から「まずは弁護士に連絡してほしい」と言われてしまい、直接やりとりすることを拒否されることが多いと思います。
その結果、相手方に伝えたいことは基本的に弁護士を通して伝える必要が生じることになります。
また、事案の内容によっては、相手方が定めた期限までに支払いや回答を行わないとしかるべき法的措置をとる(裁判所に訴訟を提起する、調停を申し立てるなど)と受任通知に記載されることもあります。
このような場合、定められた期限までに相手方の弁護士に一切連絡をとらないと、交渉に応じる意思がないと相手方から判断されてしまう可能性があります。
そうなると、相手方が訴訟の提起や調停の申立てなど次の段階の手続きを始めることにもなりかねませんので注意が必要です。
どう対処すればいいか?
相手方から上記のような受任通知が届いた場合には、まずはその内容を十分に確認してください。
受任通知には、既に述べたように、期限を定めていくらかの金額を支払うようにという記載や何らかの書類に署名・押印をするように求める記載がされていることがあります。以下で例を示します。
例1:遺産分割
たとえば、遺産分割が問題になっている場合には、相手方側が作成した遺産分割協議書が同封された通知書が届くことがあります。
この場合、内容を十分に確認せずに遺産分割協議書に署名・押印することは避けるべきです。
一度遺産分割協議書に署名・押印をしてしまうと、内容を確認して同意したものと扱われてしまい、後から撤回することは非常に難しくなります。
相手方が提示してくる遺産分割協議書は、相手方に有利な内容になっているということも考えられますので、本当にその内容で応じてもいいと考えられるかどうかを十分に検討していただく必要があります。
例2:支払いの催告
支払いが滞っている料金などがある場合、借入先(「債権者」といいます)の代理人弁護士の名義で早期に支払いをするようにとの記載がされた催告書が届く場合があります。
催告書に心当たりがあり、支払いが可能ということであればできるだけ早い時期に支払いを行うことが望ましいといえます。
しかし、複数の債権者からすでに催告書が来ており、収入状況からしても支払いが難しいということであれば、債権者と減額交渉を行う、あるいは裁判所に自己破産の申立てをして債務の免責を受けるといった対応をとる必要が出てきます。
例3:損害賠償請求
相手方の弁護士から何らかの損害が生じたとして損害賠償金を支払うように求める通知書が届く場合があります。
そのような場合、安易に言われた通りの金額の支払いをすべきではありません。
相手方の請求額はあくまで相手方が損害額を算定して示してきてい るものであり、その金額が必ずしも訴訟において認められる可能性がある範囲の金額になっているとは限りません。
言われた通りに支払いをしてしまえば、後から賠償責任の有無や賠償金の金額を争って返金を求めていくことは容易ではありません。
そのため、そもそも損害賠償責任の有無について争う余地がないのか、あるいは相手方の主張する金額が本当に適正な金額なのかについて十分に検討したうえで、どう対処していくのかを検討すべきです。
弁護士への相談を
ここまで相手方の弁護士から通知書が届いた場合の対処方法についてご紹介してきま したが、相手方に代理人がついた場合、その後のやり取りをご自身で行うことについて不安に思われる方もいらっしゃると思います。
相手方に弁護士がつけば、相手方からは法的根拠に基づいた主張がなされることになります。
そうしますと、相手方の主張が法的にみて適切なものなのかどうかを判断したうえで適切に対応する必要がありますので、法律の専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士に依頼をされた場合には、弁護士が代理人として相手方との連絡や交渉を代わりに行っていきますし、法的知識に基づいた適切な主張を行うことが可能です。
相手方の弁護士から通知書が届いた場合には、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
執筆者情報

-
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当サイトでは、相続に関するお悩みを持っている方向けに、相続をめぐる様々な事柄について解説しています。いろいろな思いを抱えておられる方も、肩の力を抜いて、何でもお話しいただけると思いますので、お気軽にご相談いただければと思います。最良の方法をアドバイスさせていただきます。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
最新の投稿
- 2026.02.03甥姪が相続できる? 具体例・必要書類や注意点を弁護士が解説
- 2026.01.07相続放棄とは?手続きの流れから注意点まで弁護士が解説
- 2025.12.23被相続人に前妻・後妻がいる場合のトラブルとその対処法
- 2025.12.23相続時に知っておきたい!遺産の使い込みとその対処法